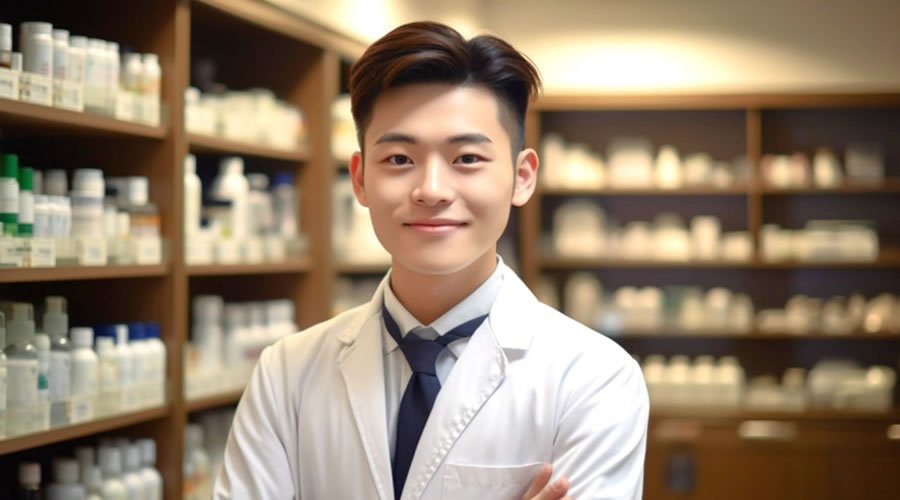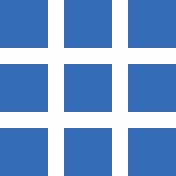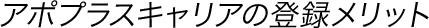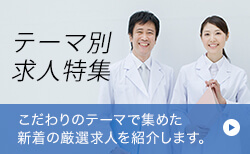薬剤師に向いている人の特徴5つ・向いていない人の特徴5つ
登録日:

薬剤師として勤務しているのに、「薬剤師に向いていない」と感じることはありませんか?この記事では、現役の薬剤師であり、薬局コンサルタントとして活躍する下田 篤男氏に、薬剤師に向いている人と薬剤師に向いていない人の特徴を5つずつ解説いただきました。また、文部科学省からも「薬剤師として求められる基本的な10の資質」が提案されています。その内容についても、わかりやすくまとめていただきました。薬剤師に向いていないと感じる方の不安解消にもつながる内容になっているので、ぜひ参考にしてみてください。
 目次
目次
薬剤師に向いている人の特徴5つ・向いていない人の特徴5つ
薬剤師にはどんな人が向いている?

薬剤師に必要なスキルや能力を踏まえると、薬剤師に向いている人の特徴は以下5つと考えられます。
- 勉強熱心な方
- コミュニケーション能力の高い方
- 責任感の強い方
- 向上心の高い方
- 几帳面で細かな作業も楽しめる方
それぞれの特徴について、以下で詳しく見ていきましょう。
勉強熱心な方
医療分野は常に進化し、新薬や治療法が次々に登場するため、薬剤師には最新の医療知識が不可欠です。薬の効果や副作用、新しい治療法を深く理解するためのセミナーや研修参加、専門書や論文を読むことが求められるでしょう。こうした日々の研鑽は、多様な患者のニーズに応え、質の高い医療サービスを提供する基盤となります。
コミュニケーション能力の高い方
薬剤師は患者だけでなく、医師や看護師、栄養士などさまざまな医療従事者と協力する機会が多いため、相手を理解し、情報を正確に伝えることが求められます。患者に対しては、薬の使用方法や注意点をわかりやすく説明し、不安を解消することで信頼関係を築くことができるでしょう。
責任感の強い方
薬剤師には責任感も求められます。薬剤師の仕事は、患者の健康に直接影響を与える薬を扱うため、少しのミスが健康に大きなリスクをもたらし、ときには生命を脅かす可能性すらあります。
処方の間違いや調剤の誤りは、患者に重大な健康被害を及ぼしかねません。したがって、薬剤師は一つひとつの業務に対して、常に重い責任感を持って取り組むことが求められます。
正確さと注意深さを維持しながら作業し、疑問がある場合には必ず確認をおこなう姿勢が重要です。さらに、責任感が強ければ、日々の業務においても倫理観を持ち、患者の安全を最優先でき、信頼を得ることができるでしょう。
向上心の高い方
薬剤師は、働きながらスキルアップや専門性を向上させる努力が求められます。たとえば、特定領域の専門薬剤師資格や在宅医療、緩和ケア、感染症対策に関する研修は、職場での役割拡大や、患者への指導のスキル向上に役立つでしょう。自己成長と新しい挑戦を続ける姿勢が、薬剤師としての能力向上につながり、結果、キャリアの選択肢を増やすことにもつながります。
几帳面で細かな作業も楽しめる方
几帳面で細かな作業を楽しめることは、薬剤師に求められる重要な資質のひとつです。薬剤師の業務には、薬の正確な調剤や患者の薬歴管理が含まれ、これらは患者の健康に直結します。細部へのこだわりは、重複投与や相互作用のリスクを避けるために不可欠といえるでしょう。また、几帳面な性格を持った薬剤師は、正確で信頼性の高い業務をストレスなく遂行し、医療チームにとって非常に貴重な存在となります。

- 下田コメント
黙々と働いている印象がある薬剤師ですが、実際には周囲とのコミュニケーションの場面が多い職業です。患者やほかの医療従事者と関わり、共感を示しながら情報を発信するといった役割が求められます。勉強する姿勢や向上心、責任感、几帳面さも大切ですが、人と関わる以上、薬剤師にとって一番大切なのは、コミュニケーション能力だと考えられるでしょう。
薬剤師に向いていない人の特徴・5つ

薬剤師として働いている場合、「自分は薬剤師に向いていないかもしれない」と感じることがあるかもしれません。薬剤師に向いていない人の特徴としては、以下の5つが考えられます。
- コミュニケーションが苦手
- 新しいことをキャッチアップするのが苦手
- 計算が苦手
- 集中力が持続しない
- 細部にこだわらない
それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
コミュニケーションが苦手
薬剤師は、患者に服薬指導をおこなったり、医師や看護師と情報を共有したりする機会が多い職業です。コミュニケーションが苦手だと、患者の質問にうまく答えられないことや、適切な情報伝達ができない可能性があります。コミュニケーションが苦手である場合には、克服するためのトレーニングや、日常から意識して対話を重ねる努力が必要です。
新しいことをキャッチアップするのが苦手
医療分野は日々新しい研究や情報が更新されるため、薬剤師として働くには、常に最新の知識をキャッチアップする姿勢が求められます。新しい薬の登場や治療法の進化に対応できなければ、患者に適切なアドバイスをおこなうことができません。新しいことをすぐに理解するのが苦手だと感じる方は、計画的な勉強法や、自分に合った学習スタイルを見つけることが大切です。
計算が苦手
計算が苦手な方は、薬剤師の仕事を辛く感じるかもしれません。薬剤師は薬の調剤業務において、正確な計算が求められます。薬の分量を間違えると、患者の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があるからです。
薬局や病院では、通常ダブルチェック体制がとられていますので、協力しあって業務を進めることも有効ですが、一人ですべての業務をこなすといった場合には注意が必要です。日頃から計算力を養えるような努力が必要になるでしょう。
集中力が持続しない
集中力が持続しない人は薬剤師に向いていません。処方せんの正確な扱いや患者へのわかりやすい指導には、注意深い取り組みが必要です。集中力が持続しないと、ミスを起こしやすくなり患者の安全を脅かすリスクが高まります。適度な休憩や効率的な集中方法、整った仕事環境が必要です。タスクを段階的に進めたり、計画を立てて効率よく業務をおこなったりすれば、集中力を養い、質の高い業務が可能になるのでしょう。
細部にこだわらない
細部にこだわらない方も、薬剤師に向いていないかもしれません。薬剤師の仕事は、小さなミスでも重大な投与ミスにつながります。ラベル誤りや重要事項の見落としを防ぐため、チェックリストを活用し確認を怠らないように、作業手順を確立し、注意力を高める練習を通じて、常に高品質なサービスを提供できる環境を整えましょう。習慣化することで、どんな状況でも安全な薬の提供が可能になるはずです。

- 下田コメント
薬剤師は求められる資質が多いと感じるかもしれません。ただ、他の多くの仕事においても必要な資質は多いものです。はじめから、すべての資質を兼ね備えている必要はありません。普段の業務から意識してコミュニケーションをとったり、自分にあったスタイルを構築したりして、克服を目指していきましょう。
薬剤師として求められる基本的な10の資質

ここまでは、薬剤師に向いている人、向いていない人の特徴を解説してきました。では、薬剤師として働くうえで必要な資質はどのように考えられているのでしょうか。令和4年に文部科学省が打ち出した「薬剤師として求められる基本的な10の資質」では、薬剤師に必要な資質を以下のように定めています。
- プロフェッショナリズム
- 総合的に患者・生活者をみる姿勢
- 生涯にわたって共に学ぶ姿勢
- 科学的探求
- 専門知識に基づいた問題解決能力
- 情報・科学技術を活かす能力
- 薬物治療の実践的能力
- コミュニケーション能力
- 多職種連携能力
- 社会における医療の役割の理解
それぞれの資質について、詳しく見ていきましょう。
プロフェッショナリズム
薬剤師は薬の専門家としての自覚を持ち、豊かな人間性と生命の尊厳を深く理解していなければなりません。薬剤師としての使命感や責任感を持ち、患者のために行動し、生活と命を最優先に考える医療や公衆衛生を実現しようと努めましょう。患者のために「誠実に働く姿勢」でいることが求められています。
総合的に患者・生活者をみる姿勢
薬剤師は単に薬を提供するだけでなく、患者の背景や生活状況をしっかりと把握する必要があります。こうしてはじめて、患者に質の高い医療や福祉、公衆衛生を提供することが可能になります。患者との関係において多角的な視点を持つことが重要です。
生涯にわたって共に学ぶ姿勢
薬剤師は、職業人生を通じて常に学び続けることが求められます。自己研鑽のみならず、他の薬剤師とも知識や経験を共有し、共に成長していく姿勢が重要です。医療の分野は常に進歩していますので、この学び続ける姿勢こそ薬剤師に求められています。
科学的探求
薬剤師は薬学的視点から医療や福祉、公衆衛生のさまざまな課題を見つけ、その解決に向けた科学的な調査や研究をおこないます。日々の業務においても科学的探求を意識し、最善の治療法を提供し続けることを目標としていくことが求められています。
専門知識に基づいた問題解決能力
薬剤師は、医薬品がどのように生命や環境に影響を与えるか、専門的に理解しておく必要があります。この専門知識に基づいて、適切な判断をおこない、さまざまな状況で薬学知識を応用していくのです。問題解決能力は、患者の健康を維持するうえでも必要不可欠といえるでしょう。
情報・科学技術を活かす能力
現代の薬剤師は、発展し続ける情報化社会の中で、人工知能やビッグデータなどの情報・科学技術を効果的に活用することが求められています。これらの新しい情報や技術を迅速に取り入れることで、医療や薬学研究をより効果的に実行することが可能になるでしょう。
薬物治療の実践的能力
薬剤師は、薬物治療を計画し、実施、そして評価する能力が求められます。患者に対して適切な医薬品を供給し、その状況に応じた調剤や服薬指導、患者中心の処方提案をおこないます。これにより、患者への治療効果を最大化することができます。
コミュニケーション能力
薬剤師は、患者やほかの医療従事者と良好なコミュニケーションを築くことが重要です。共感を持ったコミュニケーションは、患者との信頼関係を築く基礎となります。また、医療従事者と密なコミュニケーションをとることで患者の治療をよりよいものにできるでしょう。
多職種連携能力
薬剤師は多職種チームの一員として働きながら、ほかの医療従事者と対等な関係を築く必要があります。多職種で連携しチーム医療を実践することで、患者中心の質の高い医療を提供することが可能になります。ほかの職種との連携は、包括的な医療サービスを提供するために不可欠といえるでしょう。
社会における医療の役割の理解
薬剤師は地域社会だけでなく、国際的な視野に立って、予防から治療、さらにその後の管理や終末期医療に至るまで、質の高い医療、福祉、公衆衛生を担っています。社会全体の健康向上に貢献し続けることが求められています。

- 下田コメント
国が薬剤師に求めるハードルは、かなり高くなってきていることがわかります。薬剤師は、医療の進化とともに情報・科学技術を効果的に活用し、質の高い医療を提供することが求められています。
薬剤師に向いていないと思う理由は?

薬剤師として働いていると、「自分はこの仕事に向いていないのではないか?」と感じることもあるかもしれません。そんなときは、自身の状況を整理してみると、違った道が検討できるかもしれません。
やりがいを感じない
薬剤師としてのやりがいを評価する際には、自身が「1.薬剤師の仕事そのものにやりがいを見出せない」のか、それとも、「2.職場環境によって、やりがいを感じないのか」見極めることが重要です。
まず1.の場合、たとえば、薬剤師の仕事で患者との直接的な関わりが期待していたよりも大変だと感じたときなどは、仕事を続けるモチベーションが失われてしまうでしょう。また、薬剤師の業務が自身の興味やスキルと合っておらず、毎日の業務が単調で刺激がないと感じることもあるかもしれません。
こうした場合、自分の専門知識を活かせる研究開発職や、医師や薬剤師へ自社製品の良さを伝えて医療に貢献するMR、セルフメディケーションにも関わるドラッグストアでの勤務など、異なる職場環境や職務内容を探索するのも一案です。
一方2.の場合、たとえば、職場の人間関係が悪く、先輩や同僚からのサポートが得られず、孤立してしまっているケースも考えられます。また、残業が多すぎて生活の質が落ちたり、給与や待遇をほかの職場と比較して不公平に感じられたりすることも、ストレスの原因になります。
このような問題に直面しているのであれば、人事担当者や上司と話し合い、職場環境の改善を図ることが大切です。改善が測れない場合には、転職を考えることも選択肢のひとつとなるでしょう。
スキルや知識が不足していると感じる
薬剤師の仕事をするうえで、必要なスキルや知識が足りていないと感じる方も少なくないようです。これは自己成長のチャンスとも捉えることができるため、積極的なスキルアップにつながるとポジティブに考えることが大切です。
まず、自身がどのスキルや知識を強化していきたいのかを明確化しましょう。たとえば、新しい薬の知識や最新の治療法を学びたいのであれば、専門誌の購読や学会への参加、薬剤師会主催の勉強会の受講などが有効です。
また、職場内での学びの機会も活用していきましょう。先輩や上司にアドバイスを求めたり、社内研修に参加したりすることで、より実践的なスキルを習得することができます。また、日々の業務でのトライ&エラーを通じて自分の弱点を把握し、それを克服するための行動を起こすことも重要です。
コミュニケーションがうまくとれない
薬剤師としてのコミュニケーションを改善するためには、自分が日々どのように人と接しているかを振り返ることが重要です。まずは、自身の話し方や態度を振り返ってみましょう。たとえば、患者や職場の同僚と話すときに、相手の目を見てしっかりと耳を傾けているか、相手の意見や感情を尊重しているかを考えてみてください。このような基本的な姿勢を見直すだけでも、相手に与える印象が大きく変わります。
次に、積極的にフィードバックを求めることも効果的です。定期的に患者や同僚から、自分のコミュニケーションについて意見を求めることで、自己評価には気づかない改善点が見つかることがあります。たとえば、話がわかりにくいと指摘された場合は、具体的な説明や視覚的な資料を用いることで改善できるかもしれません。
最後に、患者とのコミュニケーションにおいては、特に「共感を示すこと」が重要です。患者の話をただ聞くだけになっていませんか?理解を示すために適切なリアクションをとることを心がければ、患者との信頼関係を深めることができるはずです。このように、自分自身のコミュニケーションを客観的に分析し、具体的な改善策を講じれば、薬剤師としてのコミュニケーション能力を向上できるでしょう。
薬剤師に向いていないのではなく、職場が合っていないケースも
薬剤師の仕事に就いている方が「薬剤師に向いていない。辞めたい」と感じることは、珍しいことではありません。もし、「向いていない」と感じるのであれば、その理由がどこにあるのかを考えてみましょう。
まず、現在の職場で直面している問題をリストアップします。たとえば、長時間労働や人間関係の問題、または、自分の能力やキャリアが正当に評価されていないと感じることなどがあげられます。これらの要因を探ると、薬剤師としての適性とは無関係であることも少なくありません。
ここまでで、薬剤師として自身の成長を目指すための対処法について解説してきましたが、しっかりこれらと向き合っても問題が解決できない場合、職場が合っていない可能性もあります。
たとえば、病院薬剤師から地域密着型の薬局に移ってみる、または製薬会社での業務に挑戦してみるなど、まったく違った業務環境であれば、新たなやりがいや満足感を得られるかもしれません。

- 下田コメント
転職は大きな決断ですが、自分に合った環境であるか否かは、長期的なキャリアの満足度や生活の質にも大きく影響します。逆に、転職活動をおこなうことで「今の仕事は、自身に合っている」と新たな発見につながるケースもあるかもしれません。自身にはどんな環境が一番合っているのか、改めて考えてみてはいかがでしょう。
まとめ

薬剤師に限らず、仕事が向いていないと感じるときは、まず、その原因を探る努力をしてみてください。自身で職場環境を変えることが難しいと感じるのであれば、転職もひとつの方法です。
薬剤師専門の転職エージェント「アポプラス薬剤師」は、コンサルタントがあなたの希望に沿った職場を提案してくれます。薬剤師は、ほかの業種とくらべ、多くの職種を選択できる資格です。ぜひ、自身の可能性を検討してみてください。
担当コンサルタントがあなたのキャリアに寄り添います!
転職サポートに登録(無料)監修者

薬剤師・薬局経営コンサルタント 下田 篤男
京都大学薬学部総合薬学科卒業。 卒業後は薬剤師として調剤薬局やドラッグストアグループで薬剤師として勤務。 総合病院門前などで管理薬剤師として経験を積んだのち、マネジメント業務にも携わる。現在は薬剤師として働く傍ら、医療記事の執筆、編集や薬局経営コンサルタントなどをおこなっている。
重視の求人掲載中/
働く環境を変えることで新たな発見があるかもしれません。「アポプラス薬剤師」でライフワークバランス重視の職場を見つけてみませんか?あなたに合う条件で探してみてください。
「薬剤師の悩み」に興味のある方におすすめのその他記事

- PICK UP 薬剤師を辞めたい!よくある退職理由や後悔しない辞め時の見極め方

- PICK UP 薬剤師によくある後悔!仕事への不満や転職で失敗しないためのコツ
薬剤師専門の転職サポート!32年の実績!
転職サポートに登録(無料)薬剤師のお仕事を探す
エリア別・路線別の薬剤師求人
地方から探す
都道府県から探す
| 北海道・東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 甲信越・北陸 | |
| 東海 | |
| 関西 | |
| 中国・四国 | |
| 九州・沖縄 |
人気の市区町村
| 北海道・東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 東海 | |
| 関西 | |
| 中国・四国 | |
| 九州・沖縄 |
人気の路線
| 北海道・東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 東海 | |
| 関西 | |
| 九州・沖縄 |
業種別・雇用形態別・職種別・こだわり条件別などの薬剤師求人
業種から探す
雇用形態から探す
職種から探す
人気のこだわり条件から探す
- 高年収
- 高時給
- 定期昇給あり
- 土日休み
- 年間休日120日以上
- 有給休暇取得の推奨
- 週休2.5日以上
- 住宅補助・借り上げ住宅等
- 駅チカ
- 車通勤可
- 引越しを伴う転勤なし
- 未経験・ブランク可
- 教育研修充実
- 資格支援制度あり
- 在宅あり
- 独立支援実績あり
- 漢方取扱いあり
- かかりつけ薬剤師推奨
- ママ薬剤師にぴったり
- 扶養内勤務可
- 産休・育休実績あり
- 残業少なめ
科目から探す
注目のキーワードから探す
-
1
「登録者限定求人」をすぐにご紹介します! 全体の80%以上がWEB公開していない求人。登録後、人気求人を優先的にご紹介します。
-
2
あなたの希望条件により近づける調整をします! 求人条件はあなたの「最終条件」ではありません。より希望に近づける調整が可能です。
-
3
応募から面接、就業条件の交渉まで全てお任せ! 就業中・育児中でもラクラク。企業とのやりとりは全てコンサルタントにお任せください。
お電話でのご相談も承っております。