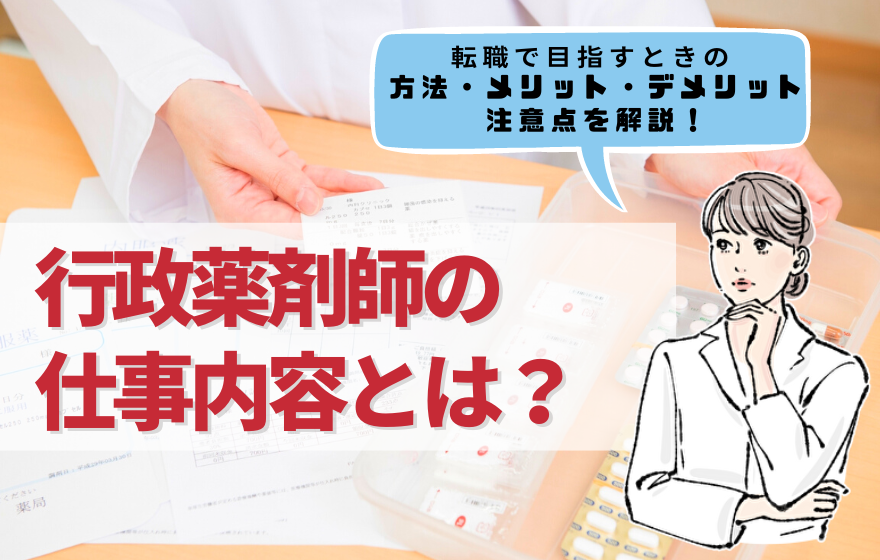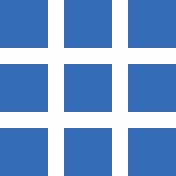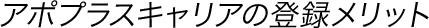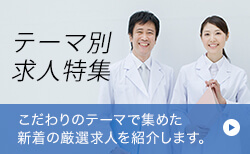薬局はコンビニより多いのに...なぜ薬剤師の就職は難しくなる?ライバルと差をつける5つの武器
登録日:

「薬剤師が飽和状態になっていて、就職が難しくなってきているってほんと?」
「薬剤師の就職事情、転職事情について詳しく知っておきたい」
このように、薬剤師の就職について、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。 事実、薬剤師の就職状況は、近年大きく変化しています。薬剤師の需要は医薬分業の飽和により、徐々に縮小していくと言われています。一方、在宅医療をはじめとする新たな場所での需要は、高まりつつあります。薬剤師が活躍できる場も多様化していると言えるでしょう。この記事では、現役の薬剤師である下田 篤男氏が薬剤師の就職事情を分析するとともに、これからの時代の薬剤師に求められるスキルや、心構えについて詳しく解説します。
 目次
目次
薬局はコンビニより多いのに...なぜ薬剤師の就職は難しくなる?ライバルと差をつける5つの武器
1.「薬剤師は就職難」は本当?

薬剤師が全体的に就職難というわけではありません。しかし、都市部のように薬剤師が充足している地域では、希望条件に沿った就職が徐々に厳しくなっています。地方と都市部では状況が異なり、需給バランスは、地域によって大きく異なります。
1-1.薬剤師は毎年増え続け、買い手市場になる
| 薬剤師国家試験 | 年度 | 合格者数 |
| 第105回 | 2020 | 9,958 |
| 第106回 | 2021 | 9.634 |
| 第107回 | 2022 | 9.607 |
| 第108回 | 2023 | 9.602 |
| 第109回 | 2024 | 9,296 |
表1:過去5年間の薬剤師国家試験合格者数(参照:厚生労働省)
2024年における薬剤師の国家試験合格者数は9,296名でした。2022年以降、薬剤師の供給は需要を上回っていると言われています。
厚生労働省の試算によると、この傾向は今後さらに加速し、2045年の薬剤師の供給過剰数は、最大で12万6,000人に上ると予測されています。10万人以上の薬剤師が供給過剰となれば、雇用側に有利な買い手市場と言えるでしょう。
ただし、現時点では、薬剤師の数が充足しているとは言い難い企業も多くあり、新卒薬剤師が就職先を見つけられない事態には至っていません。また、即戦力となる経験者の転職市場も依然として活況なため、優秀な人材に対する需要は高い状態が続いています。
1-2.薬剤師の人数には地域差がある
薬剤師の分布には明確な地域差があります。厚生労働省「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、都市部では薬剤師の数が充足傾向にある一方、地方や過疎地域は、慢性的な薬剤師不足に悩まされていることがわかります。例えば、東京都では「薬局・医療施設に従事する人口10万対薬剤師数」が235.7人で全国平均の202.6人よりも大幅に多いのに対し、沖縄県では149.4人となっています。
薬剤師の就職状況は、このように地域間格差があるため、一概に「難しい」とは言えません。薬剤師が就職しやすいかは、地域によって大きく異なります。
1-3.調剤薬局はコンビニより多い
薬剤師の主な就職先である調剤薬局の店舗数は、コンビニエンスストアよりも多いため、すぐに薬剤師全体が就職難に陥る可能性は低いと考えられます。しかし、医薬分業が飽和しつつある現状も否定できません。今後は、在宅医療への対応や健康サポート機能の充実など、より専門性と付加価値を持った薬剤師が求められるでしょう。
参照:令和4年度末現在の薬局数は 62,375 施設|厚生労働省資料 参照:2025年3月度でのコンビニ数は55,792店舗|一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
- 下田コメント
現状では求人数の多い薬剤師ですが、今後、供給過多となることは間違いありません。いまのうちから選ばれる薬剤師になるために、準備をしておく必要があります。
2.求められる薬剤師に必要な5つのスキル

今後、調剤業務だけにとらわれていると、活躍の場が限られてしまうかもしれません。医療のデジタル化や超高齢社会の進展により、薬剤師に求められる役割も大きく変化しつつあります。ここでは、真に価値ある薬剤師として認められるための重要なスキルを5つ、心構えとともに解説します。
2-1.専門領域を持ち、深い知識を追求する姿勢
今後は「ほかの薬剤師となにが違うか」という専門性が重要です。がん領域、在宅医療といった、特定の専門分野における深い知識と経験を習得すれば、ほかの薬剤師との差別化ができます。認定・専門薬剤師の資格取得も有効ですが、単なる肩書きではなく、実践的な知識と応用力を身につけましょう。
深い知識を身につけるには、専門分野の学会や研究会に定期的に参加するとよいでしょう。例えば、日本緩和医療薬学会では最新の緩和ケアに関する知見が共有されています。また、日本薬剤師会や日本病院薬剤師会が主催する専門領域別の研修会も有効です。単に参加するだけでなく、質問や発表を通じて専門家とのネットワークを構築することも重要です。
2-2.コミュニケーション能力とカウンセリング能力を磨く
高度な薬学知識も、患者に適切に伝わらなければ意味がありません。服薬指導の場面では、専門用語を噛み砕き、患者の理解度や、心理状態に合わせた説明が求められます。
特に高齢者や小児など、コミュニケーションにおいて配慮を必要とする患者に対しては、柔軟な対応力が重要です。また、患者の話をしっかり「聴く」カウンセリング技術も欠かせません。服薬アドヒアランスの向上や副作用の早期発見は、患者との信頼関係があってこそ実現します。
薬剤師にとってのコミュニケーション能力とは何か、患者様とのコミュニケーションに役立つコツ、医療従事者や職場仲間とのやりとりを円滑にするための方法などについて解説していきます。
2-3.デジタル技術を活用した業務効率化とサービス向上
業務の多くは今後、調剤支援システムやAI技術の進化により自動化されていくでしょう。これからは、こうした変化を積極的に受け入れ、業務効率化を図る姿勢も大切です。
調剤業務の機械化による業務効率化が実現すれば、時間の使い方を工夫できます。患者との対話や服薬フォロー、専門的なカウンセリングに充てる時間を増やせば、薬剤師本来の価値を高めることができるでしょう。
また、オンライン服薬指導やSNSを活用した健康相談など、新しいコミュニケーションツールにも柔軟に対応する姿勢も欠かせません。
2-4.予防医療とセルフメディケーションを実践する
超高齢社会では、疾病の治療だけでなく予防への取り組みがますます重要になっています。薬剤師も処方箋に基づく調剤だけでなく、健康維持・増進を目指して積極的にアドバイスできるスキルが必要です。
予防医療の一環としては、普段から購入しているOTC(一般用医薬品)やサプリメント、健康食品の選択に関するサポートも求められるでしょう。
また、セルフメディケーション支援(個人が軽度な体調不良を自分で適切に対処できるよう、薬剤師などの専門家が知識や情報を提供し、サポートすること)には、軽症における自己治療のサポートや、重症化の兆候を見逃さず、医療機関へ迅速に連携を図る判断力も欠かせません。今後は、処方薬とOTC(一般用医薬品)・健康食品の相互作用も含めた、総合的な薬学管理が求められるでしょう。
2-5.多職種連携とチーム医療への積極的な参画
これからの医療は、医師・看護師・薬剤師・管理栄養士といった、多職種が協働するチーム医療が中心となります。薬剤師も調剤室に留まらず、カンファレンスやラウンドに積極的に参加し、薬学的視点から患者ケアに貢献する姿勢が求められます。
特に在宅医療の現場では、訪問看護師やケアマネージャーを含むさまざまな職種と連携し、患者の生活環境に合わせた薬学管理の提供が求められます。
この記事では、現役の薬剤師が、チーム医療における薬剤師の役割について解説します。課題や問題点にも触れ、今後の薬剤師キャリアに役立つようまとめました。

- 下田コメント
薬剤師は、買い手市場へとシフトしています。従来のようにただ処方箋を待って、調剤し、お薬を渡すという業務のみでは成り立たなくなるでしょう。求められる薬剤師像を自身のなかで確立させ、日々努力していく姿勢が必要です。
3.薬剤師の主な就職先とそのメリット・デメリット

薬剤師の就職先は、多岐にわたります。各職場では業務内容、求められるスキル、労働環境、給与水準、キャリアパスが大きく異なりますので、自身の適性や価値観に合った職場選びが重要です。ここでは、代表的な5つの職場について、現状と特徴を詳しく解説します。
3-1.調剤薬局
調剤薬局業界は、医薬分業の進展とともに急速に拡大してきました。そして、近年では各地で薬局の乱立により競争が激化しています。大手調剤チェーンによる中小薬局の買収・統合も加速しているため、個人経営の薬局が差別化を図らずに生き残るのは厳しい状況です。
今後は、在宅医療への積極的な参画や、健康サポート機能の充実を図るなど、地域に根ざした特色あるサービスが求められるでしょう。
また、調剤技術以外のスキルも必要です。かかりつけ薬剤師として患者との信頼関係を構築したり、多職種と連携したりと、コミュニケーション能力が求められるでしょう。
3-1-1.調剤薬局で働くメリット
調剤薬局で働くメリットは以下のとおりです。
- 比較的残業が少ない
- 就職先は見つけやすい
- 地域医療に貢献できる
調剤薬局は比較的規則正しい勤務形態で、かかりつけ薬剤師を目指しながら、地域に根ざした医療活動ができます。
3-1-2.調剤薬局で働くデメリット
調剤薬局で働くデメリットは以下のとおりです。
- 少人数で運営しているところは休みが取りづらい可能性
- 職場が狭いため、人間関係に左右さやすい
特に、小規模薬局では人員配置に余裕がなく、スタッフ間の関係性が仕事の満足度に大きく影響します。薬局の規模や経営方針により労働環境が異なります。
この記事では、調剤薬局で働く薬剤師の業務内容・年収・キャリアパス・魅力・求められるスキルについて詳しく解説しています。
3-2.ドラッグストア
ドラッグストア業界は、大手チェーンによる調剤併設型店舗の積極展開が進んでいます。セルフメディケーションの推進という社会的背景も追い風となり、OTC(一般用医薬品)と処方薬の両方に対応できる薬剤師の需要は、依然として高い状況です。
給与水準は比較的高めに設定されていますが、土日祝日や夜間の勤務が多く、ワークライフバランスの面では課題もあります。一方、経営にも携わりたい場合、店舗管理者やエリアマネージャーを目指すことができ、キャリアアップのチャンスも豊富です。
3-2-1.ドラッグストアで働くメリット
ドラッグストアで働くメリットは以下のとおりです。
- 比較的高収入である
- セルフメディケーションに関わることができる
調剤とOTC(一般用医薬品)販売の両方に携われるほか、幅広い薬学知識を活かせます。キャリアアップの道筋も明確で、経営側に近い視点も得られます。
3-2-2.ドラッグストアで働くデメリット
ドラッグストアで働くデメリットは以下のとおりです。
- 土日平日夜間も営業しているので、生活がやや不規則になりがち
- 調剤以外の業務をこなす必要がある
小売業の性質上、シフト制による不規則な勤務体系が一般的です。調剤以外にも店舗運営や商品管理など、多岐にわたる業務を担当することになります。
この記事では、ドラッグストアで働く薬剤師の具体的な仕事内容や年収、働き方について詳しく解説していきます。
3-3.病院薬剤部
病院薬剤師の需要は、依然として高い傾向にあります。医療の高度化とチーム医療の推進により、病棟業務や薬剤管理指導、医薬品情報管理など、活躍の場は広がり続けています。
近年では、抗がん剤の無菌調製や医師への処方提案といった、より専門性の高い業務に従事する機会も増えてきました。医療の最前線で専門性を発揮できることが最大の魅力ですが、調剤薬局やドラッグストアと比較すると給与水準はやや低めの傾向にあります。
加えて、専門・認定薬剤師の取得や学会活動など、臨床薬剤師としてのキャリアアップの道も開かれています。病院薬剤部は、アカデミックな志向を持つ薬剤師に適した環境と言えるでしょう。
3-3-1.病院薬剤部で働くメリット
病院薬剤部で働くメリットは以下のとおりです。
- 医療の最前線に携わることができる
- チーム医療に積極的に関わることができる
病院薬剤部は、高度な薬物療法に関わりながら専門性を深められる環境です。また、医師や看護師と協働しながら、患者中心の医療を実践できる点も、病院薬剤部の魅力です。
3-3-2.病院薬剤部で働くデメリット
病院薬剤部で働くデメリットは以下のとおりです。
- やや給料が低め
- 病院によっては当直業務がある
病院薬剤部の給料は、ほかの勤務先と比較するとやや劣るかもしれません。また、24時間体制の医療機関では、負担の大きい夜勤や当直といった業務もあります。
本記事では、病院薬剤師の具体的な業務内容、病院で働くことの魅力、そして転職前に知っておくべきポイントを詳しく解説します。
3-4.製薬企業
製薬企業の薬剤師は、研究開発、製造、医薬情報担当者(MR)など、多様な部門で活躍しています。ほかの職種と比較すると年収が高い傾向にあり、福利厚生も充実していることが多いようです。大手企業であれば、海外勤務の機会もあり、英語力やビジネススキルをグローバルな環境で磨ける環境が整っています。
一方で、製薬業界自体は大きな変革期を迎えており、業界の再編や、働き方の変化に対応できる柔軟性が必要です。医薬品のライフサイクル全体に関わりたい場合は、やりがいのある選択肢になるでしょう。
3-4-1.製薬企業で働くメリット
製薬企業で働くメリットは以下のとおりです。
- 給料が高く設定され、福利厚生が充実
- 企業によっては豊富なキャリアパスがある
製薬企業は、薬剤師職種のなかでも待遇がよく、医薬品開発の最先端に関われる環境です。専門分野を極めるだけでなく、マネジメントを含む多様なキャリア形成が目指せます。
3-4-2.製薬企業で働くデメリット
製薬企業で働くデメリットは以下のとおりです。
- 臨床に直接関わることは少ない
- 企業によっては転勤がある
患者さんと直接関わる機会がなく、臨床現場から離れた環境です。また、大手企業では定期的な転勤があり、生活基盤が変わる可能性も考慮する必要があります。
この記事では、「薬剤師をしていて今後、製薬会社で働いてみたい」という方や、「製薬会社は、新卒じゃないと入れないのかな?」と製薬会社の薬剤師について調べている方に向け、現役の薬剤師であり、医師や薬剤師向けのコラムを多数執筆されている下田 篤男氏に、製薬会社で働く薬剤師について解説いただきました。
3-5.公務員薬剤師
公務員薬剤師には、厚生労働省や地方自治体の薬務課で働く行政職、国公立病院で勤務する病院薬剤師、保健所や検疫所で働く薬事監視員があります。最大の魅力は、安定した雇用と充実した福利厚生です。
また、行政職では、医薬品の承認審査や監視指導、薬事政策の立案など、社会全体の医療・医薬品の安全に関わる重要な役割を担っています。民間企業と比較すると給与水準はやや低めですが、社会的意義の高い仕事に携われることがやりがいとなるでしょう。
3-5-1.公務員薬剤師として働くメリット
公務員薬剤師として働くメリットは以下のとおりです。
- 安定した勤務継続が期待できる
- 地域行政に携わることができる
雇用の安定性が最大の特徴で、長期的なキャリア設計がしやすい環境です。薬事行政や保健衛生など、社会的意義の高い業務に携わることができます。
3-5-2.公務員薬剤師として働くデメリット
公務員薬剤師として働くデメリットは以下のとおりです。
- 給与水準は低め
- 入るための競争率が高い
民間企業と比較すると給与水準が低い傾向にあります。採用人数が限られているため、入職のハードルが高く、計画的な試験対策が必要です。
この記事では、行政薬剤師の特徴や仕事内容を解説し、目指す方法やメリットとデメリットを紹介していきます。行政薬剤師について理解を深めたうえで、自身の適性を見極めていきましょう。

- 下田コメント
ひとくちに薬剤師といっても、多様な職種があります。自身のキャリアパスを想定し、目標とする薬剤師像をイメージすることで、目指すべき職種を決めていくとよいでしょう。
4.業種別年収ランキング

薬剤師の年収は勤務先によって大きく異なります。下記は業種別の平均年収です。
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| 病院薬剤師 | 約390万~500万円 |
| 調剤薬局 | 約450万~550万円 |
| ドラッグストア | 約515万~600万円 |
| 製薬会社など企業 | 約550万~700万円 |
表2 薬剤師の各職種別の平均年収
※アポプラス薬剤師求人サイトに掲載している求人データを参考に、1回分のボーナス(約2カ月分として)を算出
平均年収がもっとも高いのは製薬会社をはじめとする企業で、年収550万〜700万円となっています。次いでドラッグストア、調剤薬局と続き、病院薬剤師がもっとも平均年収の低い業種です。
この記事では、薬剤師の平均年収について、男女別、都道府県別、業種別などに分けて詳しく解説します。薬剤師が年収を上げるための方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
5.薬剤師の就職活動で失敗しないための心得やコツ

薬剤師の需給バランスが変化するなか、就職・転職活動においても戦略的なアプローチが必要です。希望する職場で長く活躍するためには、自身の強みを明確にし、入念な情報収集を行い、効果的な自己アピールを行っていきましょう。また、専門エージェントの活用もひとつの手段です。ここでは、薬剤師が就職活動で失敗しないための重要なポイントを4つご紹介します。
5-1.自身の強みとキャリアビジョンを明確にする
どのような分野で活躍したいか、自身の強みはなにか、客観的に整理しましょう。短期的な目標だけでなく、5年後、10年後のキャリアビジョンを描くことで、自身に合った職場選びができ、面接でも一貫性のある志望動機をアピールできます。
自身の強みを考えるときに、以下のような事柄を自問自答するとよいでしょう。
- 学生時代の実習で最も評価されたスキルは?
- 同僚や患者から感謝された具体的なエピソードは?
- 他の薬剤師と比較して、特に得意とする業務領域は?
また、自身のキャリアをイメージする上で、自身の目標を設定する方法が効果的です。
例えば、在宅医療を志向する場合、調剤基本スキル習得(1-2年)→在宅対応薬局で経験(3-5年)→専門資格取得(5-7年)→在宅医療チームリーダー(10年~)といったように、自身の成長曲線をイメージしつつ時間軸も合わせて具体的に想定しておくとよいでしょう。
5-2.職場環境や薬局・病院の特性をしっかり調査する
入社後のミスマッチを防ぐためには、事前調査が不可欠です。給与や勤務時間だけでなく、処方箋の枚数、業務内容、教育体制、職場の雰囲気も確認しましょう。可能であれば、職場見学や薬剤師との対話の機会を設け、リアルな職場環境を把握することが重要です。事前調査が不完全だと、転職に失敗してしまいます。
例えば、給与アップと「完全週休二日制」に魅力を感じて大手チェーン薬局に転職したものの、公休は週2日でしたがシフト制で土日祝日出勤が多く、プライベートの予定が立てづらい状況だったというパターン。これは、事前に「具体的な休日取得状況」「シフト決定方法」を確認していれば防げたミスマッチでした。
転職を成功させるための事前調査では、書面や面接での情報だけでなく、実際に薬局を見学することも大切です。例えば、面接でしっかり具体的な質問をするだけでなく、待合室で30分ほど観察することで、薬剤師と患者さんのやり取りや職場の雰囲気も確認できます。事前調査を踏まえて、さらに自分の目で見ることで、リアルな職場環境を把握できるのです。
5-3.面接対策と専門性をアピールする効果的な方法
履歴書・職務経歴書は、薬剤師としての専門性が伝わるよう具体的に記載しましょう。取得した資格や実績、特に力を入れてきた業務を明確に示します。
例えば、「調剤業務、服薬指導を担当」と一般的な担当業務を書くだけでなく、「1日平均50枚の処方箋を担当。特に高齢患者への服薬指導に力を入れ、1ヶ月で多剤併用の患者20名の薬剤整理に関わり、平均2剤の減薬に貢献。」などと具体的にイメージできるような数字も合わせて記載すると効果的です。また、面接で予想される質問に対して、自身の経験や考えを簡潔に伝える練習をしておきましょう。面接本番で自信を持って自己アピールできます。
5-4.薬剤師専門の転職サイトやエージェントを活用する
薬剤師専門のエージェントは業界に精通しており、非公開求人の紹介や条件交渉のサポートなど、個人では得られない情報やサポートを提供してくれます。複数のエージェントを比較検討し、相性のよいアドバイザーを探せば、効率的かつ効果的な就職活動ができるでしょう。
本記事では、薬剤師の転職活動の準備から選考、内定後までの具体的な流れ、スムーズに転職するためのコツを解説していきます。
6.薬剤師の就職、転職には薬剤師専門の転職サイトがおすすめ
買い手市場に向かう薬剤師の就職・転職を成功させるには、専門知識を持ったサポートが不可欠です。薬剤師専門のエージェントを利用すれば、一般の転職サイトでは得られない情報や、非公開求人を提供してくれます。加えて、薬剤師としてのキャリアに関係する細かな条件面での交渉まで、多角的にサポートしてくれるでしょう。
担当コンサルタントがあなたのキャリアに寄り添います!
転職サポートに登録(無料)監修者

薬剤師・薬局経営コンサルタント 下田 篤男
京都大学薬学部総合薬学科卒業。 卒業後は調剤薬局やドラッグストアグループで薬剤師として勤務。 総合病院門前などで管理薬剤師として経験を積んだのち、マネージメント業務にも携わる。現在は薬剤師として働く傍ら、医療記事の執筆、編集や薬局経営コンサルタントとしても活動している。
薬剤師の転職に興味のある方におすすめのその他記事

- PICK UP 薬剤師のよくある転職理由は?面接での上手な伝え方も解説

- PICK UP 薬剤師が転職するときの流れは?スムーズに退職するためのコツも紹介
薬剤師専門の転職サポート!32年の実績!
転職サポートに登録(無料)薬剤師のお仕事を探す
エリア別・路線別の薬剤師求人
地方から探す
都道府県から探す
| 北海道・東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 甲信越・北陸 | |
| 東海 | |
| 関西 | |
| 中国・四国 | |
| 九州・沖縄 |
人気の市区町村
| 北海道・東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 東海 | |
| 関西 | |
| 中国・四国 | |
| 九州・沖縄 |
人気の路線
| 北海道・東北 | |
|---|---|
| 関東 | |
| 東海 | |
| 関西 | |
| 九州・沖縄 |
業種別・雇用形態別・職種別・こだわり条件別などの薬剤師求人
業種から探す
雇用形態から探す
職種から探す
人気のこだわり条件から探す
- 高年収
- 高時給
- 定期昇給あり
- 土日休み
- 年間休日120日以上
- 有給休暇取得の推奨
- 週休2.5日以上
- 住宅補助・借り上げ住宅等
- 駅チカ
- 車通勤可
- 引越しを伴う転勤なし
- 未経験・ブランク可
- 教育研修充実
- 資格支援制度あり
- 在宅あり
- 独立支援実績あり
- 漢方取扱いあり
- かかりつけ薬剤師推奨
- ママ薬剤師にぴったり
- 扶養内勤務可
- 産休・育休実績あり
- 残業少なめ
科目から探す
注目のキーワードから探す
-
1
「登録者限定求人」をすぐにご紹介します! 全体の80%以上がWEB公開していない求人。登録後、人気求人を優先的にご紹介します。
-
2
あなたの希望条件により近づける調整をします! 求人条件はあなたの「最終条件」ではありません。より希望に近づける調整が可能です。
-
3
応募から面接、就業条件の交渉まで全てお任せ! 就業中・育児中でもラクラク。企業とのやりとりは全てコンサルタントにお任せください。
お電話でのご相談も承っております。