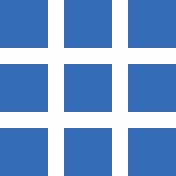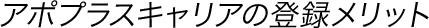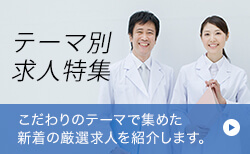新着記事一覧

絶対年収1,000万稼ぎたい!そんな薬剤師の方が就くべき就職先はどこなのか!?
薬剤師の平均年収は約510万円といわれています。国税庁が発表した、平成25年の日本人の平均給与が約413万円といわれていますから、決して低い数字ではありません。 しかし薬剤師の中には1,000万を稼いでいる方もいます。薬剤師の資格をもっている人であれば「年収1,000万」を目指すことは不可能ではないということです。では実際に年収1,000万を稼ぐためには、どんな就職先を選べばよいのでしょうか。ご紹介します。

日々高度化するがん治療に貢献する「がん専門薬剤師」とは一体...?
がん専門薬剤師は「一般社団法人 日本医療薬学会」が認定している制度です。日々進歩しているがん医療に対応できるよう"がん領域の薬物療法等に一定水準以上の実力を有し、医療現場において活躍しうる薬剤師"を養成することを目的にしています。 またこの資格は厚生労働省にも認められており、平成22年5月14日付で、薬剤師としては唯一医療法上広告が可能な専門性に関する資格としても認定されています。平成27年9月3日現在、全国には434名の「がん専門薬剤師」が存在。日本医療薬学会のホームページから、名簿を閲覧することも可能になっています。この「がん専門薬剤師」とこれに関わる研修施設などについて、ご紹介していきます。

薬剤師の初任給ってどのくらい...?実は就職先によって意外な格差が...
薬剤師として働くに当たって給料は気になるもの。特に初めて働く人にとって、またこれから薬剤師の資格をとる人にとって初任給の額は気になるところかもしれません。実は就職先によって以外な格差があるという噂もあるようです。具体的な金額について、探っていきます。

スキルアップしたい薬剤師のための「薬剤師研修センター」とは?
公益法人「日本薬剤師研修センター」は、優れた薬学的ケアを行うことのできる薬剤師を求める社会的要請に応えるために、薬剤師の生涯学習を支援し推進することを目的として、平成元年に当時の厚生省薬務局の認可のもとに設立されました。(※薬剤師研修センターホームページより抜粋) センターが主催する研修を行ったり、刊行物を発行したり、各種認定制度を実施したり、さまざまな方法で薬剤師の勉強の場を設けています。具体的にどんな研修を行っているのか、どんな認定制度があるのかなど、ご紹介していきます。

高齢化社会に必須の在宅医療。そこでの薬剤師の役割とは・・?
2014年10月1日現在の日本の人口は1億2,708万人、うち高齢者(65歳以上)の人口は3,300万人で割合は26.0%と過去最高となりました。(※内閣府 平成27年版高齢化社会白書より)このように日本は現在高齢化社会となっており、今後も一層高齢化が進むと予想されています。 高齢化が進む一方で「できる限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、安心して自分らしい生活を実現できる社会を目指す」ことが急務とされています。そんな中、薬剤師も在宅医療の現場に必要とされています。具体的な現状と薬剤師の役割についてお話ししたいと思います。

薬剤師で独立目指すにはどっちが良いの?フランチャイズVS個人薬局開業
薬剤師としていずれは独立したい・・・という方にとって「フランチャイズ」にするのか「個人薬局開業」を目指すかは大きな問題です。薬剤師の開業について、それぞれのメリット・デメリットについて考えていきます。

まだ新卒の薬剤師は買い手市場?気になる新卒採用の最新の状況は?
2006年から導入された薬学部6年制制度。文部科学省によると"医療技術の高度化、医薬分業の進展などに伴い、高い資質を持つ薬剤師養成が必要になったため"としています。薬事日報社の調査によると、実際の現場からも4年制より6年制薬剤師に対して、「実務実習を経験しているため業務知識がある」「薬学的な知識に関して探究心のある新入社員の比率が高い」「現場の仕事の習得が早い」など、評価する声が多く上がっているようです。 6年制の薬学部を卒業した学生が国家資格を取得するようになってから、3年がたちました。その間の薬剤師合格者数は97回8,641人、98回8,929人、99回7,312人、100回9,044人となっており、合計34,000人近くの6年制導入後の薬剤師が誕生したことになります。この状況を踏まえ、新卒採用の状況はどうなっているのか、考察していきます。

これから薬剤師国家試験受ける方は注目!合格率を上げるための3大ポイント!
薬剤師の合格率は、薬学部が6年制に移行してから低下傾向にありました。2015年の第100回薬剤師国家試験の合格率は63.17%で、ようやく合格率低下に歯止めがかかったといわれています。 薬剤師の合格率は、大学別・新卒・既卒など細かく分けて発表されています。厚生労働省が発表した第100回の合格者数の資料によると、合格率が80%を超えた大学は106 校中わずか6校。「金沢大学」「広島大学」「明治薬科大学」「名城大学」「近畿大学」「福岡大学」となっています。一方で30%台の学校は4校、20%台の学校も1校あり、大学によって格差がでているようです。日本のトップ大学といわれる「東京大学」でも61.90%となっており、薬剤師の国家試験は難関のようです。 では合格率を上げるための3大ポイントについて、考えてみます。

薬剤師の求人は自分で探すより紹介が有利?メリデメまとめました。
薬剤師の求人情報は、比較的数多くあります。自分で探す、知人に紹介してもらう、紹介してくれる会社を利用する、などさまざまな方法で仕事を探すことができますが、希望どおりの求人を探すためにはどの方法が一番有利だと思われますか? 薬剤師求人の探し方について、メリット・デメリットをまとめてみました。

目指せ認定薬剤師!自己研磨の証はこんなにも就職に有利だった!?
認定薬剤師とは、日本SMO協会や日本医学薬学会などさまざまな団体が独自に行っている認定制度を取得した薬剤師のことをいいます。薬剤師は国家資格で、認定資格は民間の資格になりますが、だれにでも取得できるものではないこと、専門分野に特化していることが認められる自己研磨の証でもあることから、実は就職する際にも有利に働く場合があるようです。 さまざまな認定資格があることをまずは知っていただければと思います。
-
1
「登録者限定求人」をすぐにご紹介します! 全体の80%以上がWEB公開していない求人。登録後、人気求人を優先的にご紹介します。
-
2
あなたの希望条件により近づける調整をします! 求人条件はあなたの「最終条件」ではありません。より希望に近づける調整が可能です。
-
3
応募から面接、就業条件の交渉まで全てお任せ! 就業中・育児中でもラクラク。企業とのやりとりは全てコンサルタントにお任せください。
お電話でのご相談も承っております。