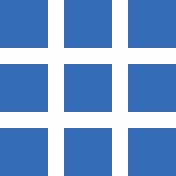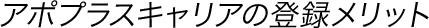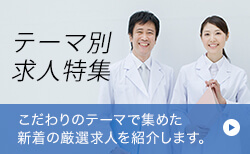新着記事一覧

これで調剤をスマートに解決!薬局向けスマートフォンアプリ「ヘルスケア手帳」について
薬局で使える新しいシステム、「ヘルスケア手帳」というアプリがあることを ご存じでしょうか。 薬局の利用者である患者さんが処方箋を撮影し薬局に送付することで、 スムーズに薬を受け取れるようにできるというシステムです。 2014年7月15日に、パナソニックより発売されたサービスですので、すでに導入 されている薬局もあるかもしれません。 ▼薬局向けに「ヘルスケア手帳」サービスを販売 http://news.panasonic.com/jp/topics/2014/38572.html 利用者である患者さんにとってはもちろん、薬剤師さんにとっても便利な アプリですので、内容についてご紹介します。

かかりつけ薬局の上をいく!?健康情報拠点薬局とは?
厚生労働省が2015年6月4日に、「健康情報拠点薬局(仮称)」を導入する意向を発表したのをご存じでしょうか?政府は医療費抑制政策として、さまざまな提案を打ち出していますが、これもそのうちのひとつです。具体的に「健康情報拠点薬局」とはどういうものなのか?薬剤師はそこでどんな役割を果たすべきなのか?お話しします。

処方箋をもらってから薬局まで遠い!!そんな悩みは近々解消するかもしれません!
薬剤師をはじめ、医療関係者なら「医薬分業」という言葉はご存じのとおりです。しかし内閣府が行ったインターネット調査によると、一般の方で「医薬分業」という言葉を知っている人は47.8%となっており、半数程度にとどまっていることがわかります。医薬分業という考え方の元、現在は処方箋を扱う薬局が遠い場所にある場合も多いようですが、それに対して不満をもっている方もいらっしゃいます。そこで医薬分業について一部見直す案がでており、2016年1月27日には「医療機関と薬局の間にフェンスを設置するといった一律の構造規制を見直す」ことなどが提案されました。▼毎日新聞「医薬分業 規制見直し案」参照 http://mainichi.jp/articles/20160128/ddm/002/040/165000c 見直すにあたってどんな背景があったのか、一般の方の医薬分業に関する意識はどうなのかなど、考察していきます。

大手ドラッグストアの門前薬局にあやしい影が...調剤基本料引き下げによる影響とは??
医薬分業の考えのもと院外処方が浸透し、調剤薬局の数は近年増加しました。タウンページのデータベースによると、2003年が49,616件だったのに対し毎年徐々に増加。2011年には52,735件になりました。さらに2012年は一気に4,000件ほど増加し56,516件となっています。▼タウンページデータベース「薬局の登録件数推移」参照 http://tpdb.jp/townpage/order?nid=TP01&gid=TP01&scrid=TPDB_GL01 一方でいわゆる大手調剤薬局グループ(20店舗以上の保険薬局を保有する薬局開設者)の数は、2013年に210グループになり、 店舗数は14,484店、全国の調剤薬局の26.0%を占めるまでになりました。 ▼矢野経済研究所「調剤薬局グループに関する調査結果2014」参照 https://www.yano.co.jp/press/press.php/001294 そんな中、大手ドラッグストアの門前薬局には、2016年「調剤基本料引き下げ」という厳しい報酬改定が行われるようです。 ▼NIKKEI DRUG INFORMATION「大手チェーンの門前薬局は調剤基本料を引き下げ」参照 http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/trend/201601/545561.html?bpnet この背景にあるのは何なのか?考察していきます。

これから薬剤師の評価は患者が決める時代に?かかりつけ薬局制度案とはいかに?
「かかりつけ薬局」という言葉を聞いたことがある薬剤師の方は多いと思います。患者さんに対して処方箋に基づいた薬を調剤するだけではなく、薬歴管理を行ったり、健康管理を行ったりしてくれるような薬局が、これまでの「かかりつけ薬局」のイメージでした。ところが2015年9月14日、厚生労働省がついに「かかりつけ薬局の制度案」をまとめたのです。▼日本経済新聞「かかりつけ薬局、24時間対応など条件」参照 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS14H74_U5A910C1EE8000/ 早ければ、新制度は2016年からスタートするといわれています。今後は薬剤師の評価を患者が決める時代になるのでは?といわれる制度案。具体的にどういった内容なのか、この制度により薬剤師は何を求められていくのか、考えていきます。

薬剤師の調剤過誤による健康被害が!そんなとき薬剤師の責任ってどれくらいあるの?
薬剤師の調剤過誤はあってはならないことです。しかし人間が行うことですから、100%ないとは言い切れません。実際、調剤過誤により薬剤師や薬局側に責任があるとして判決が下されたこともあります。刑事責任・行政責任・民事責任など、さまざまな責任が考えられますが、必ずしも薬剤師ひとりにくだるわけではありません。 薬剤師として「調剤過誤」を起こさないためにどうすればよいか、万が一起こってしまったときにどう対応すればよいかなど、考えていきたいと思います。

薬剤師が進めるセルフメディケーションとは?今密かに注目されている療法をご紹介
セルフメディケーションの定義は"自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること"です。▼厚生労働省「世界保健機構WHOの定義」参照http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/06/02.html 病気になったらすぐに病院に行くのではなく、薬の専門家である薬剤師などに相談し「自分で薬を選び治療する」こともセルフメディケーションです。また、そもそも病気にかからないよう「規則正しい生活をする」「健康に関する正しい知識をもつ」ことも、セルフメディケーションのひとつといえます。 そんななか薬剤師が進める「セルフメディケーション」がいくつかあります。OTC医薬品について適切な説明をすることはもちろん、今秘かに注目されている療法などをご紹介します。

衝撃ニュース!調剤薬剤師ではなく、事務が調剤している薬局が実際にあった...!?
昨年6月に、厚生労働省から以下のような通達が日本病院薬剤師会会長宛に届きました。その内容は"今般、薬局において、薬剤師以外の者が軟膏剤の混合を行っていた事案が明らかとなりましたが、当該事案を含め、少なくともこうした軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を薬剤師以外の者が直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても同条(薬剤師法第19条)への違反に該当するとともに、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等への違反に通じる行為であり、薬局に対する国民からの信頼を大きく損ねるという点でも大変遺憾です"というものでした。▼「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」参照 http://www.jshp.or.jp/cont/15/0629-1.pdfPDF つまり、薬剤師の資格をもたない人物が調剤を行っている薬局があったことになります。 この事案についてご紹介するとともに、調剤薬剤師の仕事について改めて考えていきたいと思います。

製薬会社の薬剤師になったらやっぱりMR営業ってしなくてはいけないの...?
薬剤師の平均年収は531万円といわれていますが、製薬会社の場合、約400万円~800万円ともいわれ、高収入の職場といえます。(年収ラボ参照)そのため製薬会社への入社を希望する薬剤師の方も多いと思いますが、MR職すなわち営業をしないといけないのはちょっと・・という方もいらっしゃるかもしれません。しかし薬剤師が製薬会社に入った場合、必ず営業職につかなくてはいけないのでしょうか?製薬会社での薬剤師の仕事についてお話しします。

日本では薬剤師に処方権は存在しない?処方権が与えられたら薬剤師はこんなこともできる!
日本の薬剤師に処方権がないということは、みなさんご存じのとおりです。処方権は医師にあり、医師の書いた処方せんに従い薬剤師は調剤を行います。薬剤師の役割は「医師の処方に間違いがないか」「患者の既存の薬との重複はないか」などのチェックをすることになっています。 しかし海外では、処方権が与えられている薬剤師も活躍しています。日本では薬剤師に処方権を与えることには消極的なようですが、もし処方権が与えられたらどうなるのでしょうか?処方権をもつ海外の薬剤師の実態について調べながら、考察します。
-
1
「登録者限定求人」をすぐにご紹介します! 全体の80%以上がWEB公開していない求人。登録後、人気求人を優先的にご紹介します。
-
2
あなたの希望条件により近づける調整をします! 求人条件はあなたの「最終条件」ではありません。より希望に近づける調整が可能です。
-
3
応募から面接、就業条件の交渉まで全てお任せ! 就業中・育児中でもラクラク。企業とのやりとりは全てコンサルタントにお任せください。
お電話でのご相談も承っております。